[業界今昔物語]
第3回 ランドリー機械 発達の歴史1
明治、大正時代には、洗濯の量を示す方法として、関西では一丁、二丁洗いなどと呼んでいました。
一丁は樽一杯をいい、二丁とは樽二杯分を洗えるということです。
そのうち、洗濯機の直径とその長さをもって、二尺五寸×三尺五寸などの表示も使用されましたが、外胴の径か内胴の径か明示されなかったため、機械メーカーによってまちまちな表示もありました。
その後、被洗物を収納する内胴の径×長さが正しい表示として統一されていきました。
その当時の米国の洗濯機は径×長さをインチで表示していたという文献もあります。
日本ではメートル法が成立して、内胴の寸法がメートルで統一され、機械メーカー各社もユーザーもこれに従いました。
さらに洗濯できる一回の理想的容量が容積によってキログラムで表わされるようになって、国内の基準もでき、外国製の機械との比較も容易になりました。
しかしユーザーの要求や据え付け面積などの制約から、機械メーカーは受注生産が主体であり、量産は不可能な状態で、機械コストは高く、弱小業者には高嶺の花でした。
そして業法が施行され、標準型は20キロとなり、メーカーも量産体制ができるようになりました。
競争力でコストも下がり、機械は普及していきました。
ここでは、1キロの洗濯物は、標準型ワイシャツ4枚分の重さ(乾燥重量)で換算されました。
すなわち、業法型20キロ洗濯機はワイシャツ80枚分と換算されたわけです。
シーツならシングルが700グラム、ダブル1,200グラムなどと、被洗物の量を簡単に計算できる時代に入ったのです。
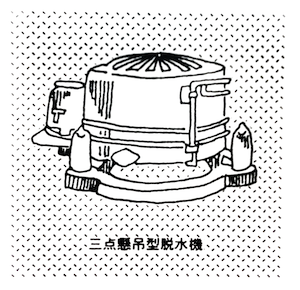
それでも機械は、標準型の20キロのほかにも30、40、50、80、100キロなど種類は多くありました。
内胴、外胴の寸法が市販のメッキ鋼板、真ちゅう板などから有効に板取できるものが価格的には安く、板を溶接したり切り落としたりしたものは高価でした。
機械を駆動するには脱水機と電動機を共用する、あるいは同じ洗濯機を並列にして駆動できるよう、天井の長いシャフトからベルトによって回転させ洗濯機には自動反転式装置を取り付け、遊車も利用しました。
そのため機械台数の多い工場では洗濯機、脱水機の数だけベルトがかかり、それぞれの機械は浮き上がらないように、長いアンカーボルトでコンクリート床に強固に固定されていました。(B ・K)
